熱中症に対する教育や訓練
現場責任者や職長だけでなく、作業者に対しても、熱中症の症状・予防方法、救急措置、災害事例などの労働衛生教育を行うことが重要です。
熱中症が発生するしくみや、緊急時の対応を知っておくことは、作業員の命を守ることにつながります。
また、体調不良を申告しやすい環境や、気軽に相談できる雰囲気をつくっておくこと、日頃から救急措置の訓練を行っておくことも大切なことです。
労働衛生教育
熱中症予防のために、各級管理者、労働者に対する教育を実施しましょう。
教育は、熱中症予防管理者向けの労働衛生教育として3時間半のカリキュラム示されています。また、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際にも熱中症の予防対策について繰り返し実施するとよいでしょう。
教育用教材としては、厚生労働省の「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」もご活用ください。
厚生労働省 職場における熱中症予防情報
当協会の「熱中症予防教育」のご案内
熱中症予防管理者等の業務
衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は熱中症予防管理者に対し、次の業務を行わせることとされています。
- 作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。
- 暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
- 入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある。
- 朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。
- 作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
- 熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
- 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
- 退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。
熱中症の事例
【事例1】
(50代男性/7月上旬に発生)早めの昼食を摂った後の午前11時から暑熱職場で作業を開始。2人の作業者で交替で麦茶を摂りながら作業していた。作業で大量の汗をかいていた午後3時に右手と両足が筋けいれんを起こし、動けなくなって医療機関を受診した。以前から糖尿病を指摘されていたが未受診であり治療は受けていなかった。
【事例2】
(20代男性・7月中旬に発生)午前10時前から炎天下で高負荷の作業に従事した。午前11時半ごろに気分不良とふらつきが出現し、医療機関を受診した。休憩はなかったがスポーツドリンクを合計3杯飲んだ。体調不良はなかったが、前日夜に飲酒があり、朝食を摂っていなかった。
【事例3】
(40代男性・8月上旬に発生)午前8時半から炎天下で高負荷の作業に従事した。午前9時半までに大量の発汗があった。午前10時半から10分間ほど炎天下の車中で休憩した。休憩後に再び炎天下で作業を行った。午前11時半にめまいと虚脱感を自覚し、自発的に休憩したところ手足のしびれが出現し動けなくなって医療機関を受診した。朝食は摂っており体調不良はなかったが、前日から睡眠不足であった。
その他の事例は、下記リンクをご覧ください。
職場でおこる熱中症|職場における熱中症予防情報 (厚生労働省HP)
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
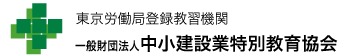
このページをシェアする
講習会をお探しですか?